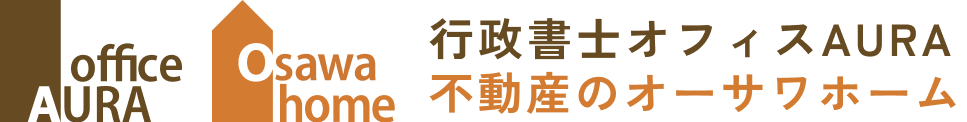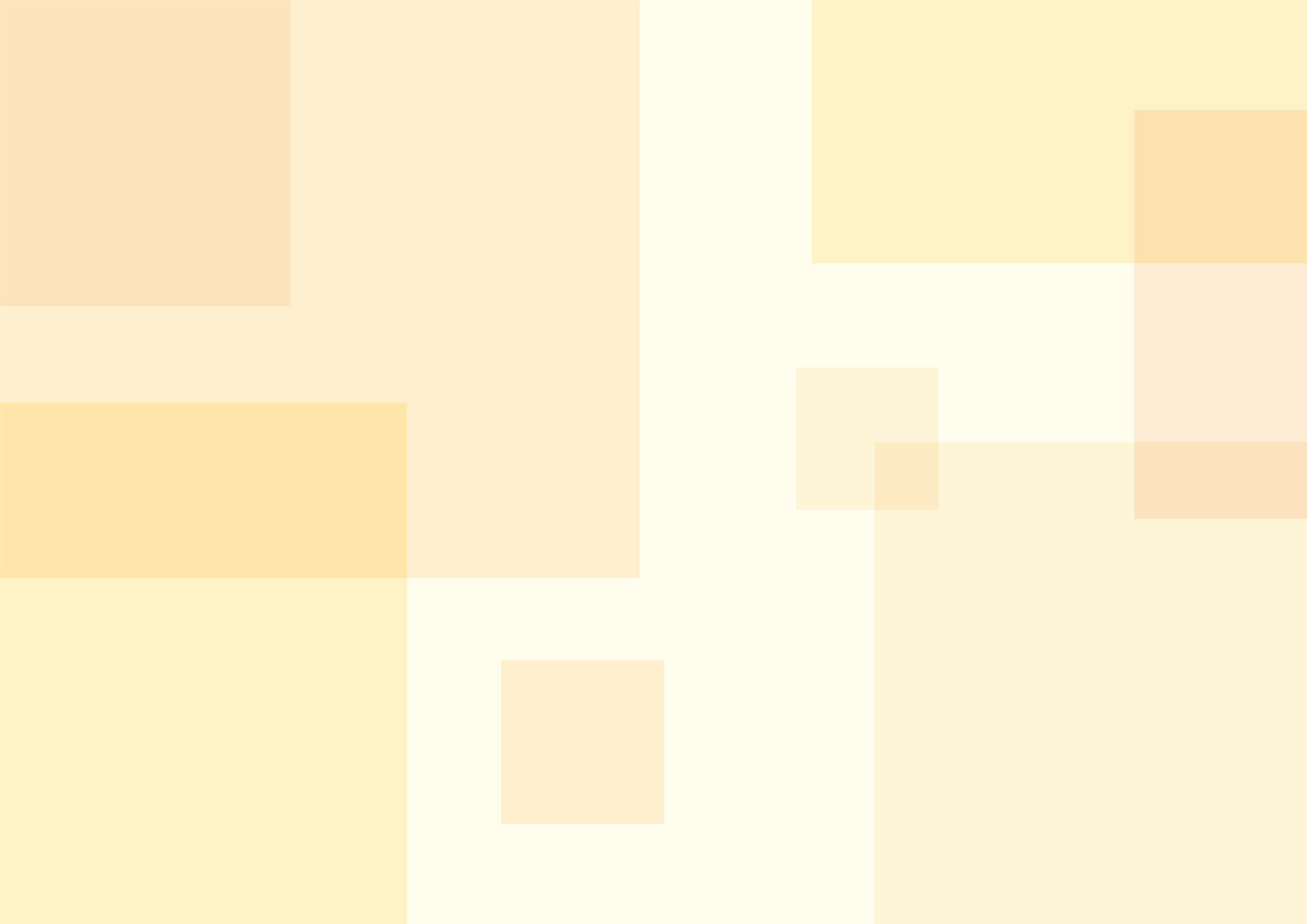いつもご覧いただきありがとうございます。
昨日、2025年9月24日(水)に、「お薬の嫌いな薬剤師」である田尻理恵さまとのコラボイベントを開催させていただき、今回はそこでお話しさせていただいた内容をご紹介させていただければと思います。
ご来場いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
前回コラボさせていただいた永岡一代さまと同様、取り返しのつかない事態になる前に個別の事情に合わせ正しい予防策を提唱するという共通テーマを主体とした催しでした。
以下に早速、その内容についてお伝えしていきたいと思います。
相続と聞くと「うちはそれほど財産がないから大丈夫」と思う方も多いかもしれません。
でも、公的なデータを見ても、当オフィスが対応してきた案件から見ても、「うちは普通の家庭」だと思っているご家庭こそ相続で揉めることがとても多いのです。
今日は、最高裁の司法統計を使って、その“普通家庭のトラブル実態”と、皆さんがお家でできる生前対策のヒントをお伝えします。
“普通の家庭”でトラブルが多いという事実
最高裁の「司法統計年報(家事編)」から、家庭裁判所に到達して調停・審判で決着したケースを、最近の4年(令和3年~令和6年)のデータを当所で集め直したところ、以下のような結果が出ました。
| 年度 | 総数(認容・調停成立) | 1,000万円以下 | 1,000〜5,000万円以下 | ≤5,000万円合計 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年 | 6,934 | 2,279 | 3,037 | 5,316 | 76.66% |
| 令和4年 | 6,858 | 2,297 | 2,935 | 5,232 | 76.29% |
| 令和5年 | 7,234 | 2,448 | 3,166 | 5,614 | 77.60% |
| 令和6年 | 7,903 | 2,810 | 3,354 | 6,164 | 78.00% |
| 直近4年合計 | 28,929 | 9,834 | 12,492 | 22,326 | 77.18% |
直近4年合計:28,929件中22,326件 → 約 77.18% が「遺産総額5,000万円以下」のケース。
しかもそのうち、
直近4年合計:28,929件中9,834件 → 約 33.99% が「遺産総額1,000万円以下」のケース。
なんと「遺産総額1,000万円以下」のケースが全体の三分の一も占めているのです!
この数字から見えるのは、「資産が多くない家庭でも」むしろ、「資産が多くない家庭のほうが」相続トラブルが起きているということです。
この事実を知ってもなお、皆さまは、「うちはそれほど財産がないから大丈夫」と感じますか?
どうして“揉める”のか?実際によくある原因
数だけではピンと来ないと思いますので、実務でよく見かける“揉める理由”をいくつか挙げます。皆様のお家でも「あ、これ心当たりがあるかも」と思うものがきっとあります。
- 不動産が入っていると評価や名義、共有の割合、住まいの居住権などで意見が分かれやすい。
- 生前に親が子に援助したり介護したりしたことがある場合、「どれだけ寄与したか」「特別に受けた助けがあるか」などで主張がぶつかる。書面や証拠があいまいだと係争が長引く。
- 再婚家庭・連れ子・兄弟姉妹間での“遠方に住んでいる人”“疎遠になっていた人”など相続人関係が複雑だと、話し合いでひとつの方向を決めるのに時間がかかる。戸籍や相続人の特定でつまずくことも。
- 遺言がない、あっても内容が漠然としている(たとえば「資産の一部を孫に」「使ってほしい人へ」など具体性に欠けるもの)ため、遺言書作成時の形式・文言で争いが起きたり、裁判所で遺言の有効性をめぐる議論が必要になったりする。
今日からできる“備え”のこと
揉めるリスクを少しでも減らすために、今からできることがあります。負担が大きくなる前に、一歩ずつ進められることを意識しましょう。
- 公正証書遺言を作る
誰に何をどれだけ渡すかを明確にしておくこと。形式の不備で無効・争点にならないよう、専門家に相談のうえ公証役場を使う方法が安心です。 - 任意後見契約や委任契約を整える
判断能力がまだ十分なうちに、“誰が財産管理をどのようにするか”“臨時の代理権範囲”などを決めておくと安心です。 - 不動産・名義・登記・借入(抵当関係)の整理
建物や土地の名義が共有名義・抵当権設定・未登記等だと、相続時に分割や換価(売却)が難しくなります。 - 重要書類をまとめ・家族で話をしておく
通帳、保険証券、借入契約、登記簿謄本、戸籍などを整理し、「この財産を子どもにどうしてほしいか」など希望を家族で共有しておくと誤解が減ります。
親として・子どもとして心がけてほしいこと
- 「親が元気なうち」に準備を進めること。とくに認知症など判断能力が落ちる前が大事です。
- 「親に任せる」「親がなんとかしてくれるだろう」と期待しすぎないこと。親も家族も思い違いがトラブルのもとになります。
- 初めは小さな話から。希望や不安を一言でいいので共有することが、あとで大きな合意を作るベースになります。
まとめとメッセージ
相続というのは、決して“お金持ちだけの話”ではありません。公的なデータが示す通り、「遺産総額5,000万円以下」のご家庭でこそ、多くのトラブルが起きています。「まだ早い」「うちは大したことない」はリスクを見逃す言葉。
私たちは、このような“普通の家庭に起きる相続問題”の実務を多数扱ってきました。
不動産を含む相続対策は専門性が高く、法律・税務・実務調整が絡むことで難しい部分が多いため、経験と知識が役立ちます。
相続対策は親が認知症等になる前に行う必要があります。家族だけで抱えず、話しづらいことを一人で悩まず、“専門家の無料相談”を活用することをおすすめします。親を信じて待つだけではなく、具体的な準備を一歩ずつ始めてみませんか?
出典:最高裁判所「司法統計年報(家事編)」令和3〜令和6年 第52表「遺産の価額別」による当所での集計。数値・割合は当所計算。
話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。
また、公正証書遺言や任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体・不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。
「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。
だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。
収拾のつかない紛争となってしまう前に、、、
無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。