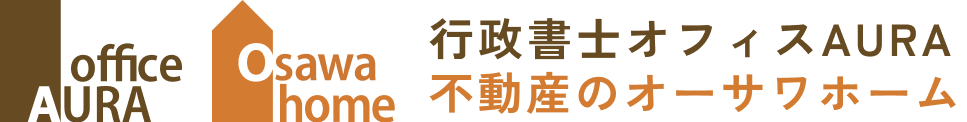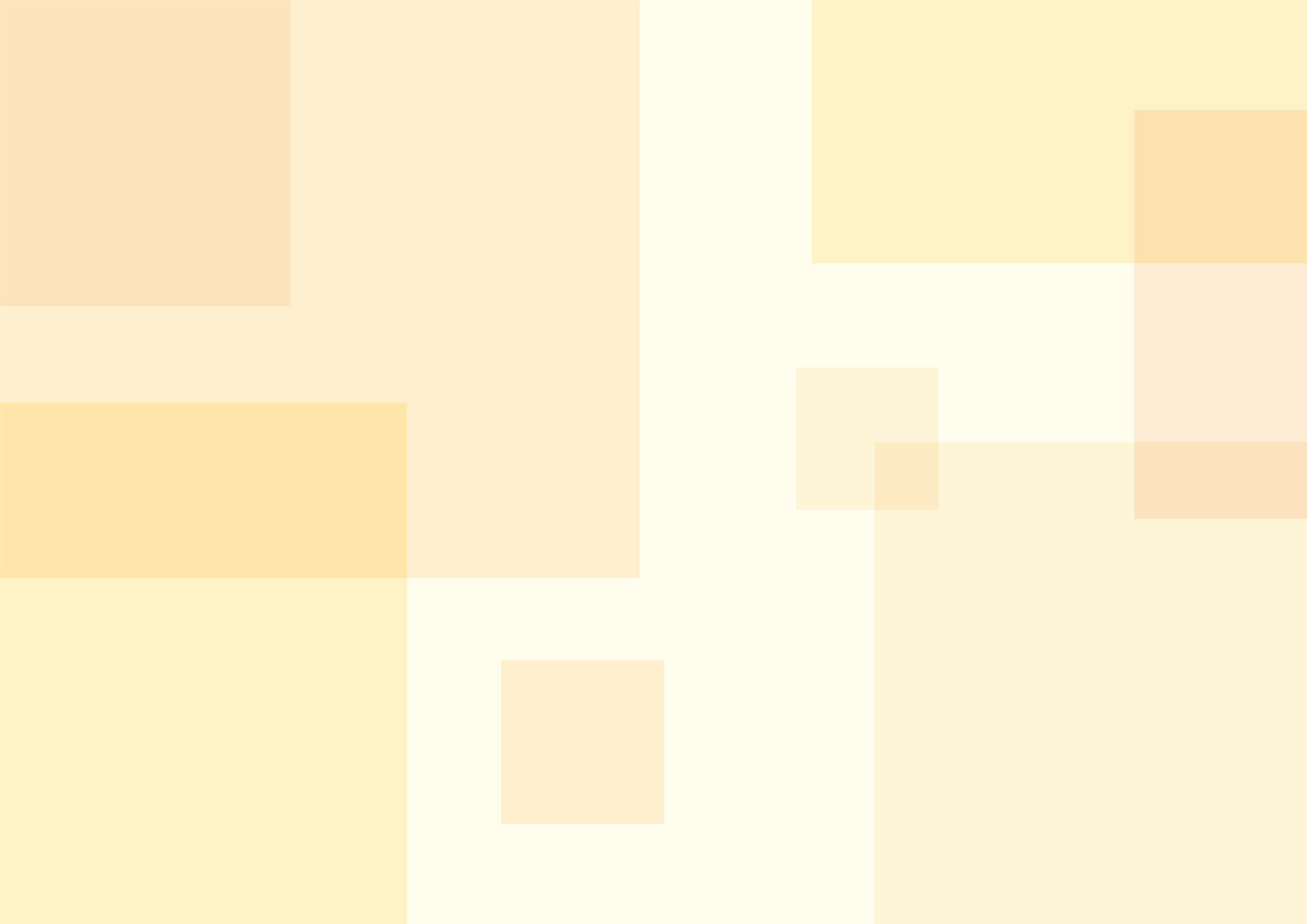いつもご覧いただきありがとうございます。
大切な方が亡くなったら、、、
死亡後の主な手続きチェックリスト(不動産編)
― 不動産の名義変更・相続手続きを期限・内容別に整理 ―
大切な方が亡くなった直後、深い悲しみの中で不動産を含む多くの手続きを進めなければならない現実に、戸惑うご遺族は少なくありません。
「名義変更はいつまでにしなければならないのか?」
「相続登記って必ず必要なの?」
「不動産を売るには何から始めればいいの?」
こうした不安を少しでも軽減するために、不動産に関係する主な手続きを時系列ではなく、手続きの内容や義務・期限ごとに整理し、チェックシート形式でまとめました。
特に、令和6年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、従来以上に注意が必要です。
特にその注意の内容に、将来的な登記費用を削減することだけに着目し、名義変更を急いだ結果、その後被相続人、相続人が意図しない相続配分となるようなことが発覚するケースも増えており、決して手続きのみに着目するのではなく、民亊法務と不動産の両方の実務に精通する専門家への早期ご相談が大変重要であると言えます。
相続登記完了後は正当な理由がない限り、原則、取消不能であるからです。
また、過去にもお伝えしてきたように、遺言があればすべて安心、というわけではありません。
特に不動産が絡む場合は、登記、税務、現物管理、売却、処分などの多面的な視点での手続きが重要です。
【ご利用方法】
- ご家族が亡くなられた後、不動産に関する手続きの「何を・いつまでに・どこに」届け出・申請すべきかを一覧にまとめました。
- 内容は法改正に対応し、2024年4月以降の最新制度に基づいています。
- 必要に応じて✔を入れながら、抜け漏れ防止にご活用ください。
- 相続人や不動産の状況によって必要な手続きが異なります。不明点がある場合は、当オフィスまでお気軽にご相談ください(※一部の手続きについては代理申請にも対応しています)。
チェックリスト本体(不動産編)
相続登記関連(義務あり)
| 手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
|---|---|---|---|
| 相続登記(所有権移転登記) | 不動産を相続したすべての相続人(遺言がある場合も含む) | 法務局(登記所) ※当オフィスで、法定相続証明情報ならびに遺産分割協議書類の作成や相続手続き相談及び司法書士との連携、ご紹介により登記手続の完了を支援 | ☐ |
| 相続登記の申請期限 | 相続が発生したことを知った日から3年以内(2024年4月1日施行) | ※正当な理由がない限り、期限超過には過料(最大10万円)の可能性あり | – |
| 遺産分割協議がまとまらない場合 | 協議が未了でも法定相続分での登記申請義務あり | 法務局 | ☐ |
相続人申告登記(代替措置)
| 手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
|---|---|---|---|
| 相続人申告登記 | どうしても相続登記が間に合わない場合の簡易的な手続き(1回限り) | 法務局(登記所) ※当オフィスから司法書士をご紹介して、登記手続完了までを支援 | ☐ |
| 申告期限 | 相続の開始を知った日から3年以内 | 法務局 | ☐ |
不動産の処分・管理関連
| 手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
|---|---|---|---|
| 固定資産税の名義変更・納税通知先の変更 | 相続登記が済んでいない場合も必要 | 市区町村役所(資産税課) | ☐ |
| 解体・売却・仲介手続き | 空き家・不要な不動産がある場合 | 不動産会社 ※当オフィスでは解体~売却まで一括支援が可能です | ☐ |
| 賃貸中の不動産の契約・賃料管理 | 故人が大家(賃貸人)であった場合 | 管理会社/相続人 | ☐ |
相続関係の準備・前提手続き(登記の前提)
| 手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
|---|---|---|---|
| 被相続人の戸籍収集・法定相続情報一覧図の作成 | 相続登記や金融機関手続きの基本資料 | 法務局(一覧図)・市区町村(戸籍) ※当オフィスにて代行取得可能 | ☐ |
| 遺産分割協議書の作成 | 遺言がない、または一部指定で不動産が含まれていない場合 | 相続人間の協議により作成 ※当オフィスで文案作成・証明書類の整備を支援します | ☐ |
| 評価証明書・固定資産税課税明細書の取得 | 相続登記・相続税の算定に必要 | 市区町村役所 | ☐ |
税務関連
| 手続き内容 | 該当する場合 | 手続き先(窓口) | ✔ |
|---|---|---|---|
| 相続税申告・納税 | 課税額がある場合(基礎控除:3,000万円+法定相続人×600万円) | 税務署 ※土地評価・不動産譲渡予定がある場合は、提携税理士と連携可能です | ☐ |
| 準確定申告(所得税) | 故人に不動産所得(賃料収入等)がある場合 | 税務署 ※提携税理士をご紹介 | ☐ |
【補足欄】
- 相続登記の義務化(令和6年4月〜)により、これまで放置されがちだった空き家・空地も対象になります。名義変更の放置は将来のトラブルや売却不能の原因になりますので早めの対応を。
- 相続人申告登記はあくまで「登記義務の一時的な回避策」であり、真の解決ではありません。
- 不動産の売却・活用を視野に入れる場合は、相続手続きだけでなく、現地確認・境界・権利関係の確認・整備が必要です。当オフィスでは不動産売却に伴う仲介・解体・不用品処分、また測量・表題登記などの専門家である土地家屋調査士との連携支援もワンストップで対応可能です。
このチェックリストは、ご家族を亡くされた後の不安や混乱を少しでも軽減できるよう、不動産に関わる相続手続きの実務に特化して整理したものです。
「登記の義務があるのは分かるけれど、誰に相談していいか分からない」
「不動産の名義を変えた後、どう管理・処分すればいいのか…」
そんなときは、どうぞ当オフィスへお気軽にご相談ください。民亊法務に強い行政書士事務所としての手続き支援に加え、不動産の専門家として実務的な解決策をご提案いたします。
話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。
また、公正証書遺言や任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体・不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。
「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。
だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。
収拾のつかない紛争となってしまう前に、、、
無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。