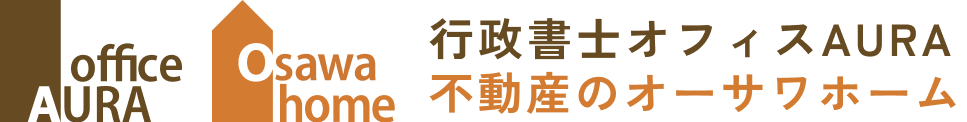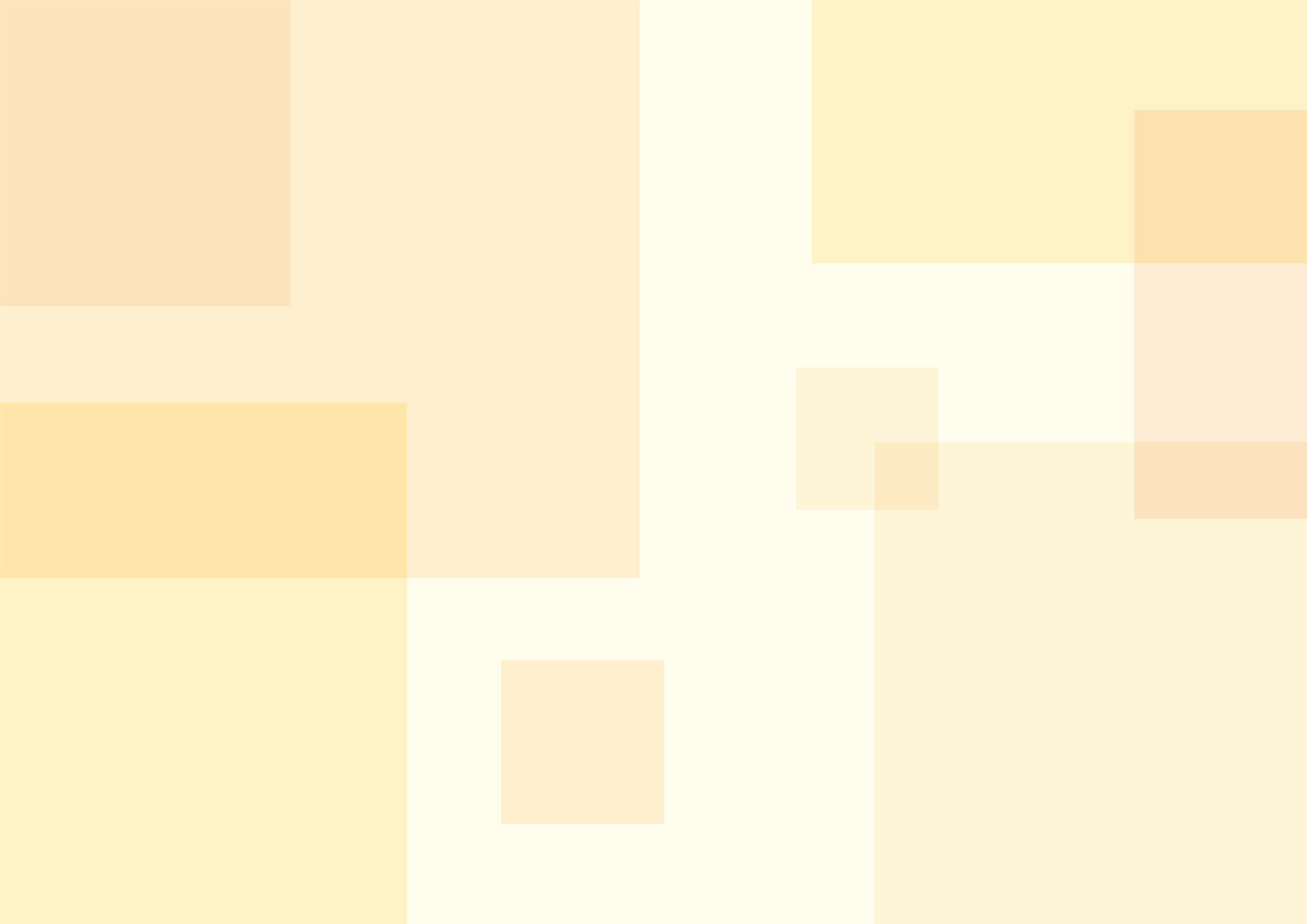いつもご覧いただきありがとうございます。
私、清永は、過去20年以上大手上場企業の生命保険募集人として1万件を超える面談に携わってきました。
当時、顧客への保険金支払い事務等を対応するなかで、保険契約の民法上の取り扱いや判例、法律などの知識が不十分であったため、ケースによっては顧客や自身に対して明確な「解答」をすることができず、力不足を痛感した経験があります。
現代、金融商品を取り扱う業界のほとんどがお客様本位の業務運営を行うことを宣言しており、それに実直に応えるセールスパーソン、またその顧客にとっても大変重要なテーマである「生命保険と相続の関係」について、今回はお伝えしていこうと思います。
生命保険と相続の関係
─ 家族の想いを「争い」にしないために ─
「家族に迷惑をかけたくない」
「自分がいなくなったあと、少しでも役に立てたら…」
そんな願いから生命保険に加入される方は少なくありません。
生命保険は、遺された家族への最も確実なメッセージであり、経済的な支えになると同時に、心の安心にもつながる大切な備えです。
でも実はこの保険金が、相続のときにトラブルの原因になってしまうことがある――
そんなことが、現場では珍しくありません。
今回は、**「生命保険金は相続とどう関係するのか?」**という素朴だけれど大事なテーマについて、一般の方にも、保険のご提案をされている方にも、わかりやすくお話ししたいと思います。
1.保険金は「遺産」ではない?
まず、基本のキホンから。
被相続人(亡くなった方)を被保険者(保障の対象者)とする生命保険について、保険金受取人に指定されたものは、保険金請求権を保険契約者または被保険者から承継的に取得するものではなく自己固有の権利として原始的に取得するものと解されています。(大審院昭和6年2月20日判決、最高裁判所昭和40年2月2日判決)
したがって、原則、死亡保険金は性質上保険金受取人の固有の財産であり、被相続人の相続財産には含まれないことになり、遺産分割協議の対象とはなりません。
遺産分割の対象にならないとは、つまり、ほかの相続人が「自分にも分けてほしい」と言ってくる権利も、基本的にはないということです。
☑ 受取人を指定していれば、保険金はその人のものになる
☑ 遺産(現金・預貯金・不動産など)とは別の扱いになる
この仕組みがあるからこそ、生命保険は「確実に渡したい人にお金を残せる」手段として、とても有効なのです。
2.「相続人」と指定した場合と「受取人無し」の場合はどうなるの?
生命保険の契約書に、受取人として「相続人」とだけ記載されているケース、あるいはそもそも受取人の記載がない(=無指定)というケースがあります。
この2つは一見似ているように思えますが、実務上の扱いには明確な違いがあります。
● 共通している点
どちらも、亡くなった方の時点での相続人が保険金を受け取る対象になるという点では共通しています。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、3人が対象になります。
ただし――
● 違いが生じるポイント
「相続人」と明記されている場合:
→ 保険契約に基づき、相続人一人ひとりが“固有の権利”として保険金を取得することになります。
これは、最初から相続財産とは別の「保険金受取権」としての性質を持つということです。
受取人が無指定の場合:
→ 保険金の受取先が契約上どこにも決まっていないため、一度「相続財産」として扱われ、相続人全員で遺産分割協議を行う対象になります。
つまり、他の財産と同様に分割協議が必要になり、スムーズに受け取れない可能性が高くなります。
このように、同じように「家族に渡る」と思われがちな2つのケースでも、相続の手続きや受取人の権利の扱いが異なるため、注意が必要です。
3.遺留分ってなに? 保険金にも関係あるの?
生命保険金は、原則的に「特別受益」にはあたりません。なぜなら、保険金請求権は、民法903条に規定される「遺贈」や(生前)「贈与」にあたらないとされているからです。
しかしながら例外もあります。
到底是認できないほど、相続人間の不公平が著しいと評価すべき「特段の事情」がある場合には、例外的に生命保険金が特別受益(生前に受けた贈与)となり得る、すなわち、あまりにも偏った保険金の受け取りは、遺留分の計算に含めるべきだという判断が出されました。(最高裁判所の平成16年10月29日判決)
遺留分とは、「相続人が最低限もらえるはずのお金」のこと。民法で定められていて、配偶者や子どもなどには原則として一定の取り分が認められています。
ですので、この例外的な事例のことを全く考慮に入れずに生命保険を活用し、相続設計をしていた場合には、遺留分侵害額請求を受けることもあり得るのです。
4.もめないための3つの工夫
生命保険は、「争族」を避けるための力強いツールです。
でも使い方を間違えれば、かえって火種になることも……。
そんなことにならないために、以下の3つのポイントを意識しておくと安心です。
✔ 受取人はハッキリと指定する
→受取人はきちんとした指名や続柄を具体的に記載しておくことで、あとで争いになりにくくなります。
✔ 相続人同士の気持ちに配慮する
→ 特定の人に保険金が集中するなら、公正証書遺言で付言事項などを記載し、他の人への明確な気持ちを示しておく。
✔ 遺留分を意識した金額設計を
→ 高額な保険契約をするときは、法的に問題がないか、専門家と一度確認しておくと安心です。
5.おわりに
生命保険は、お金のためだけのものではありません。
「大切な人に、ちゃんと想いを届けたい」
そんなやさしさを形にできる、かけがえのない道具です。
だからこそ、その設計には法律と感情、両方への配慮が欠かせません。
保険のプロの皆さま、
そして、生命保険をご活用の皆さま、保険について真剣に考えておられる皆さまへ。
現存の保険契約を不必要に解約することなく大切にしながら、想いを“争い”にしない相続設計を、経験豊富な当オフィスが可能な限り、お手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。
話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。
また、公正証書遺言や任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体・不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。
「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。
だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。
収拾のつかない紛争となってしまう前に、、、
無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。