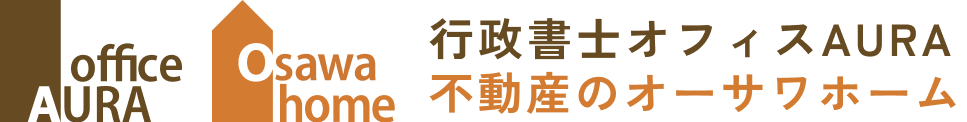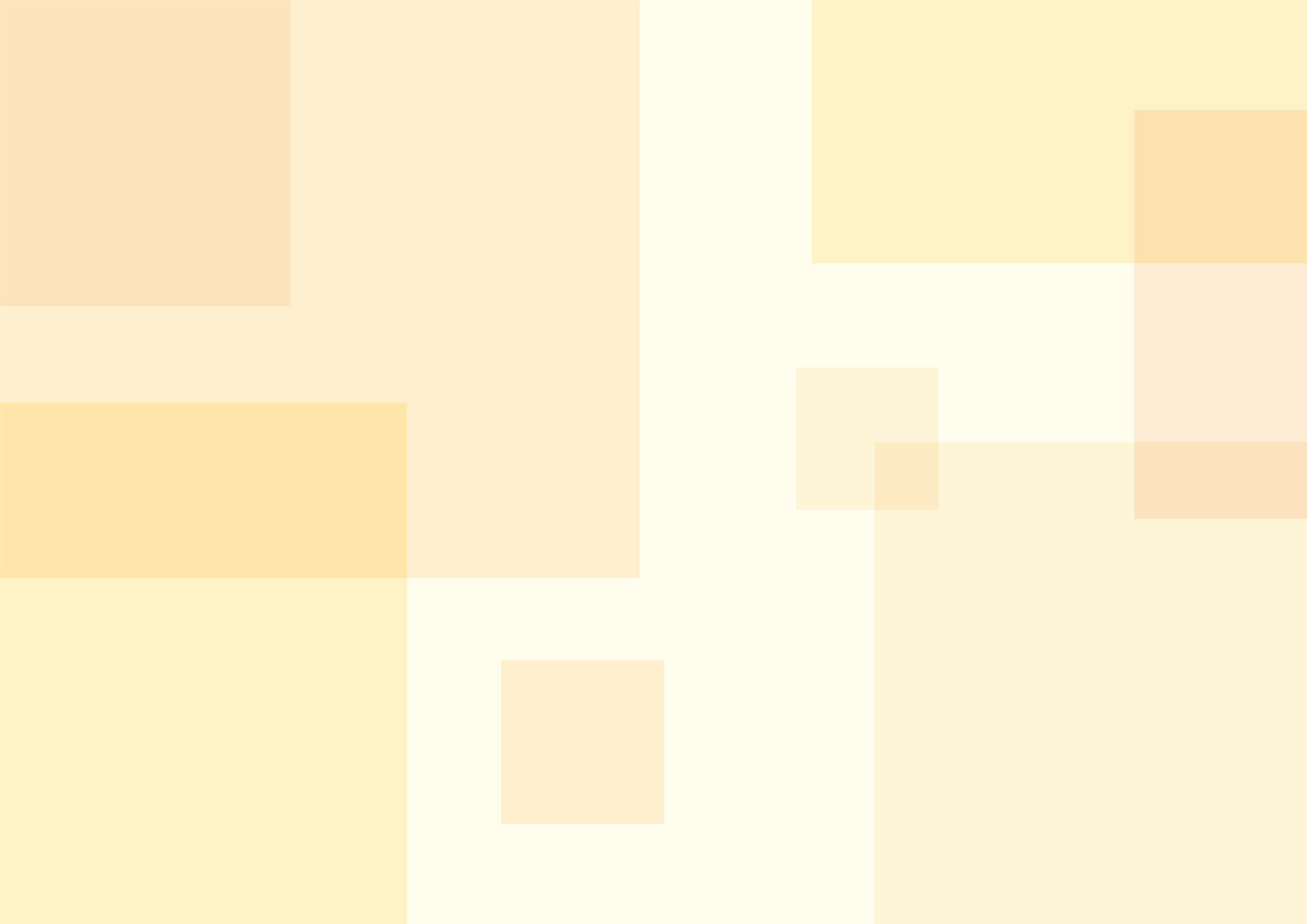いつもご覧いただきありがとうございます。
相続は、遺された家族が亡き方の思いを受け継ぐ大切な手続きです。しかし、準備がなされていないことで、家族の間に深刻な対立が生じ、「争続(そうぞく)」へと発展するケースが少なくありません。
当オフィスでは、今回ご紹介するケースに該当、又は類似する場合には、生前に遺言公正証書や任意後見契約・委任契約を作成しておくことを強く推奨しております。
「相続」が「争続」に変わる典型的なケースは、法定相続人の構成や人間関係、財産の内容によって、次のようなパターンに分かれます。
まず今回は、簡潔にその5つのケースのそれぞれの背景にある「争いの種」と予防策をご紹介し、
次回よりこの代表的な5つのケースを個別に分け、それぞれの権利者の感情や心情を丁寧に描きながらストーリー形式の文章でお伝えしてまいります。
1.【子どもがいない夫婦】兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケース
背景:
子どもがいない夫婦(父母や養子等がいない場合)には、配偶者以外に、被相続人の兄弟姉妹やその子(甥・姪)が法定相続人になります。普段あまり交流のない親族が突然相続人になるため、遺産分割が難航することがあります。
争続の種:
- 高齢の配偶者に生活費が必要でも、兄弟姉妹が遺産分割に同意しない
- 家や預金を巡って協議がまとまらない
予防策:
2.【再婚・連れ子】前妻・後妻、異母・異父兄弟姉妹がいるケース
背景:
前婚の子と現配偶者、あるいは再婚相手との子どもなど、複雑な家族構成では相続人間の利害がぶつかりやすくなります。
争続の種:
- 前婚の子と後妻が顔も合わせたことがない
- 感情的な対立から遺産分割協議が破綻
- 不動産の共有や処分方針が合意できない
予防策:
3.【行方不明者・不仲な相続人】協議が成立しないケース
背景:
相続人の一人が連絡が取れない、あるいは家族関係が悪く話し合いができない場合、遺産分割協議が行えず、長期化することがあります。
争続の種:
- 不在者財産管理人の申立てが必要
- 意見が合わず、家庭裁判所での調停に発展
- 遺産の管理や維持費負担が生じる
予防策:
- 事前に【公正証書遺言】で配分を指定
- 【死後事務委任契約】により信頼できる人に手続きを任せる
- 財産処分の指示を明記し、トラブルを最小限に
4.【相続財産の大部分が不動産】分割しにくい財産構成
背景:
遺産の多くが不動産であると、共有状態の解消や売却を巡って対立することがあります。
争続の種:
- 誰が住むか、どう処分するかで意見が割れる
- 相続登記を放置し、数十年後に相続人が激増してしまう
- 修繕・管理費用を巡る負担の押し付け合い
予防策:
- 不動産の処分方針を記した【公正証書遺言】
- 売却後の分配や管理を第三者に委ねる【委任契約】
- 死後の処理を任せる【死後事務委任契約】
5.【被相続人が賃貸住宅で死亡】家財処分や契約解除が必要なケース
背景:
持ち家ではなく、賃貸住宅にお住まいだった方が亡くなると、部屋の明け渡しや家財処分など、急を要する事務手続きが相続人に発生します。
争続の種:
- 家財の処分方法で揉める
- 誰が管理・支払いをするか不明確
- 管理会社との対応に追われる
予防策:
- 死後の事務を明記した【死後事務委任契約】
- 処分・費用負担の方法を決めておく
- 公正証書で事前の意思を明示
まとめ図
| ケース | 争いの原因 | 主な予防策 |
|---|---|---|
| 子なし夫婦 | 知らない親族が相続 | 遺言、公正証書、後見契約 |
| 再婚・連れ子 | 感情的対立 | 遺言、遺言執行者、後見契約 |
| 不仲・行方不明 | 協議ができない | 遺言、死後事務委任契約 |
| 不動産のみ | 分割困難 | 処分方針を遺言で明記 |
| 賃貸住まい | 契約解除・処分対応 | 死後事務委任契約 |
話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
当オフィスでは、ご相談者さま方にしっかりと寄り添い、「話し合いの場づくり」のお手伝いをします。
- 家族だけでは切り出しにくい「相続の話題」に、専門家として第三者の立場から同席
- 相続人となる方々の立場や気持ちを整理しながら、話し合いを前向きに進めるための助言
- 判断能力があるうちに、公正証書遺言・任意後見契約・委任契約などの準備をスムーズに実施
相続や遺言のご相談は、「民亊法務の専門家」と「実務の現場」を知る当オフィスにお任せください。
当オフィスでは、行政からの許認可を受けたうえで、遺言・相続・任意後見契約などの民事法務を中心に、書類作成から公正証書の手配まで一貫して対応しております。
さらに、不動産の売買、建物の解体、不用品処分、遺品整理、不動産の相続手続き、名義変更に関する書類作成のご支援までワンストップでの対応が可能です。
法律だけでなく、現実に必要となる作業までを一括でご相談いただけるため、ご家族の負担を最小限に抑え、安心して将来に備えることができます。
「まだ早いかも」と思った今こそ、最適なタイミングです
相続準備は、「何か起きてから」では間に合わないことが多くあります。
「家族のもめごとを避けたい」「今は元気だけど、いずれに備えたい」
そう感じたときが、準備を始めるベストタイミングです。
「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。
だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。
無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。