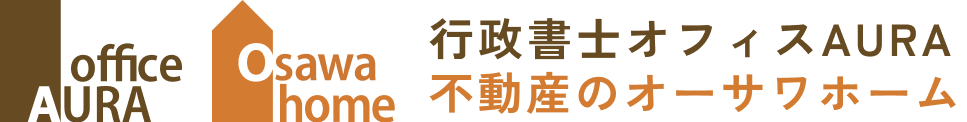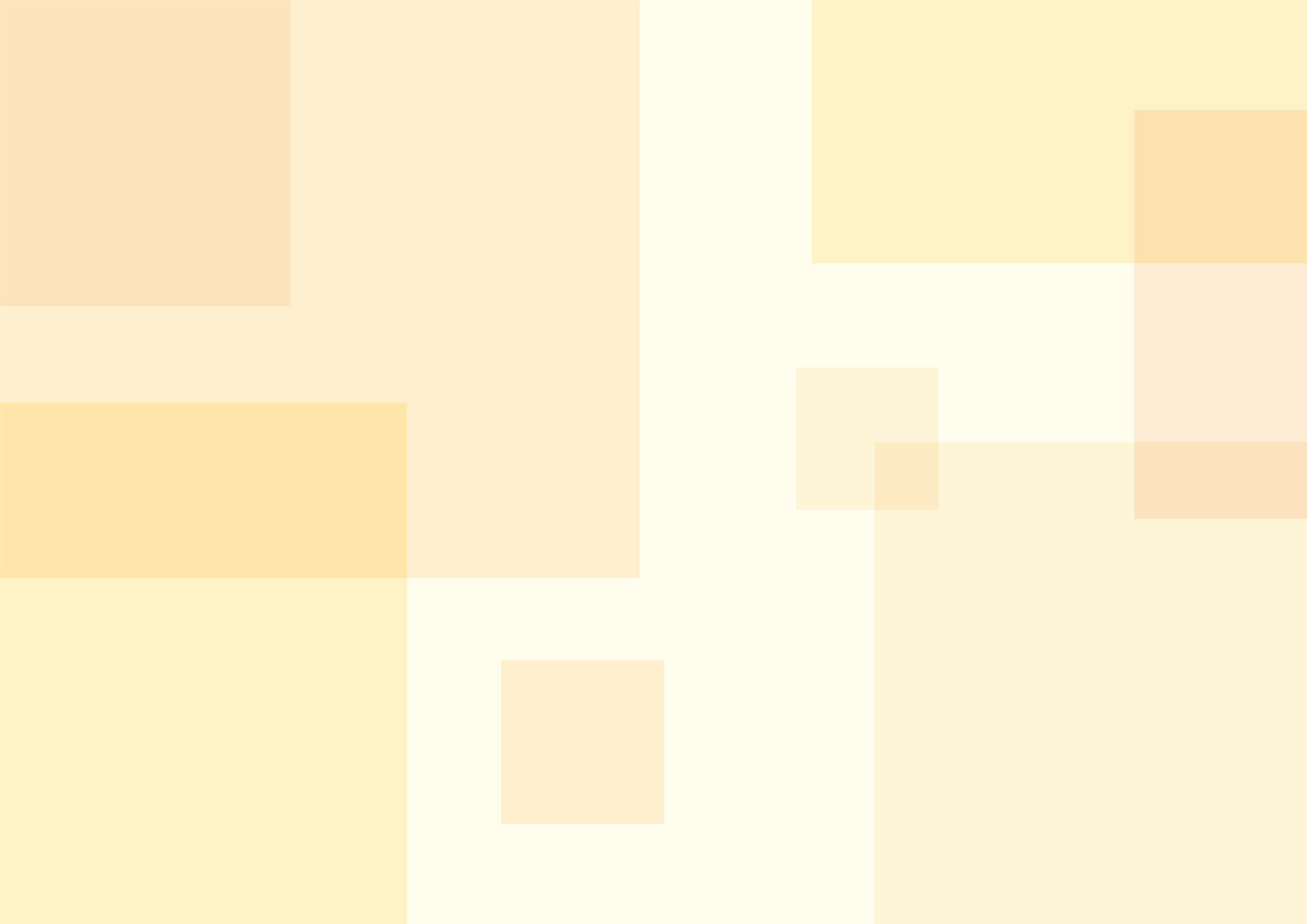いつもご覧いただきありがとうございます。
相続した不動産の固定資産税納税通知書に記載の建物面積の表記が、当該不動産の建物の一部を過去に増築した記憶があり、記載されている面積よりも、現況の建物面積のほうが大きい場合、増築部分が未登記である可能性があります。
目次
1.継続保有を希望する場合
今後も継続して保有を希望されているとしても登記簿上の建物面積と、実際の建物の現況に明らかな差異がある場合、その部分が未登記である可能性があります。
▍①登記をし直すべきか?
- 原則として、「建物表題変更登記」等により、建物全体を現況にあわせて登記することが望ましいです。
- 特に次のようなケースでは登記し直すことが推奨されます:
| 推奨される理由 | 内容 |
|---|---|
| 相続登記後の整合性確保 | 今後の遺産分割や売却・担保設定時のトラブル防止 |
| 建物の評価・保険加入時の正確性 | 火災保険・地震保険の面積判断にも影響 |
| 固定資産税の評価の適正化 | 現状より低く評価されている可能性がある |
→ 当オフィスでは土地家屋調査士と連携し、調査と登記手続きを一括サポート可能です。
▍②登記後に必要な行政手続き(資産税関係)
- 建物登記が完了すると、法務局から市町村に通知が行きます。
- その後、市町村(資産税課)より以下の対応を求められる場合があります:
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 家屋調査申告 | 家屋評価の見直しのための申告書提出(必要な市町村のみ) |
| 職員の現地確認 | 評価額確定のための実地調査(事前連絡あり) |
▍③追徴課税は発生する?
- 原則として、増築部分に対する固定資産税の再評価がなされる可能性はあります。
- ただし、以下の通りです:
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 遡及課税の上限 | 最大5年間まで遡及課税の可能性(地方税法第17条の5) |
| 課税の対象 | 増築部分に対する未評価分のみ(既存部分には影響なし) |
| ペナルティの有無 | 故意でなければ加算税や過料の可能性は通常なし |
| 増額の程度 | 増築がかなり古ければ評価額はかなり低く、税負担も大きくはなりません |
登記後の固定資産税見直しは避けられませんが、誤差の修正という扱いです。大きな負担増にはなりにくいと考えられます。
2.売却を前提とする場合に必要なご対応について
▍①登記簿と実際の建物が違うままでは売却に支障が出ます
- 売却する際、登記簿上の建物面積と実際の建物面積が違う場合、買主へ事前に説明が必要になります。
- 未登記部分の有無は「重要事項説明書」にも記載義務があります。
- 未登記のまま売却すると、契約後のトラブルや価格交渉の対象になりやすくなります。
▍②登記し直す(登記変更)べきか?
→ 基本的には、土地家屋調査士に現地調査を依頼し、登記し直すことを強く推奨いたします。
登記の方法
「建物表題変更登記」や「増築部分の新築登記」などの対応が必要です。
→ 当オフィスでは土地家屋調査士と連携し、調査と登記手続きを一括サポート可能です。
▍③登記後に必要な行政への手続き
- 建物の変更登記が完了すると、法務局から自動的に市区町村(資産税課)へ情報が通知されます。
- ただし、自治体によっては以下の手続きを求めることがあります:
- 「家屋調査申告書」の提出(必要な市町村のみ)
- 担当者による現地確認への立ち会い依頼
▍④追徴課税の可能性について
- 原則として、固定資産税は最大 過去5年まで遡って追徴される可能性 があります(地方税法第17条の5)。
- ただし以下の点で、過度に心配する必要はありません:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 故意性 | 故意に申告を避けたわけでなく、古い増築である点が評価されやすい |
| 建物評価 | 増築が古い場合、経年により評価額はかなり低い |
| 加算税等 | 通常は、延滞金・過料の対象とはされません(あくまで修正扱い) |
3.当オフィスでの売却支援体制(重要事項説明書の作成を含む)
貴不動産の売却等にあたり、以下のようなワンストップ対応が可能です:
| ステップ | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| ① | 現況調査・ヒアリング・登記簿の確認 | 行政書士(当オフィス) |
| ② | 土地家屋調査士との連携による現地測量と登記支援 | 弊所紹介士業 |
| ③ | 必要に応じて役所への申告・届出 | |
| ④ | 登記後、現況面積・建物情報に基づく「重要事項説明書」の作成 | 宅地建物取引士(当オフィス) |
| ⑤ | 売買契約書の作成支援(瑕疵担保・現況優先の記載) | 宅地建物取引士(当オフィス) |
すべての手続きを当オフィスで一貫してお手伝い可能ですので、安心して売却を進めていただけます。
現在の建物面積と登記簿が異なるため、まずは調査と必要な登記変更を行いましょう。
その後、市区町村への届け出を行えば、売却に向けた正確な情報で重要事項説明が可能になります。