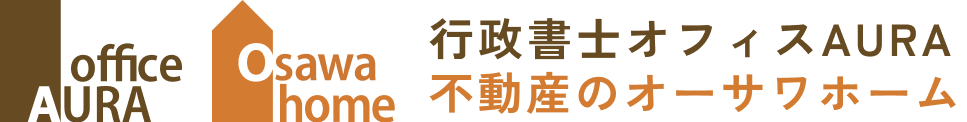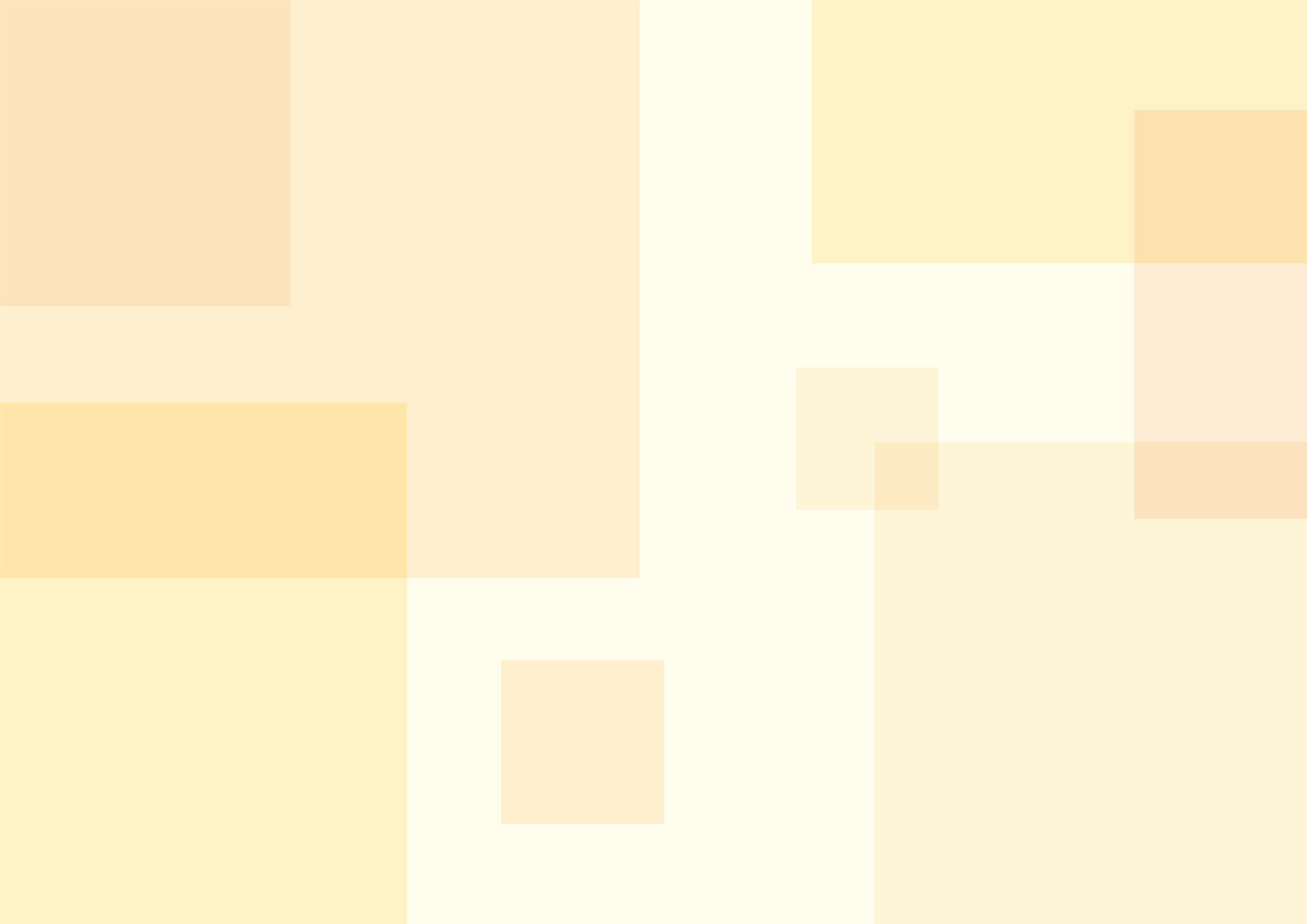いつもご覧いただきありがとうございます。
本日より、タイトルは業務報告とせず、直近の業務でご相談者さまに対してご説明をさせていただいた内容などを、改めてご理解いただきやすいよう整理してタイトル化し、その詳細を当該ご相談者さま、あるいはご関心がある方々に向けてお伝えしていこうと思います。
なお個人情報などにつきましては特定されることが無いよう配慮しておりますのでご安心下さい。
1.後見制度について
今回の内容はまず前提として任意後見契約、法定後見制度及び委任契約の違いをご認識いただくことによりご理解が深まりますので、まずは違いについて簡潔にご説明いたします。
■ 任意後見制度(本人が元気なうちに備える)
・本人が判断能力のあるうちに、将来の後見人(例:家族、専門職)を自分で選んで契約する制度です。
・判断能力が低下したとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約に基づいて後見が開始されます。
・契約内容に従って、財産管理や生活支援を行います。
主な特徴:
✔ 後見人を自分で決められる
✔ 支援の範囲を契約で自由に設定できる
✔ 本人の希望が尊重されやすい
■ 法定後見制度(判断能力が失われてから)
・本人がすでに認知症等で判断能力が不十分な状態になってから、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
・原則として、家庭裁判所が選任した後見人が、法定のルールに従って財産や身上の管理を行います。
・家族が後見人になれない場合や、第三者(弁護士・司法書士等)が選ばれることもあります。
主な特徴:
✔ 家庭裁判所がすべてを判断・監督
✔ 本人の意思が反映されにくいことがある
✔ 申立や手続きに時間・費用がかかる
■ 委任契約(本人が元気なうちに任せる)
・本人が判断能力のあるうちに、信頼できる人(例:家族、専門職)に対して、財産管理や各種手続きなどを任せる契約です。
・契約締結後すぐに効力が発生し、本人の意思に基づいて支援が開始されます。
・本人が認知症などで判断能力を失うと、契約の効力は原則として失われます。
主な特徴:
✔ 任せる相手を自分で選べる
✔ 委任内容を自由に決められる
✔ 判断能力がある間は柔軟な対応が可能
2.公正証書遺言と併せて、任意後見契約・委任契約を整えておく意味
相続人同士の不仲や行方不明者がいる場合、公正証書遺言を作成しておくことで、遺産分割協議を避けることができ、相続手続きを円滑に進めることが可能となります。
加えて、その作成時に任意後見契約および委任契約を結んでおくことで、本人が将来、判断能力を失った際にも、信頼できる人が事務や財産の管理を継続的に行えるようになります。
この三契約を同時に整備することで、元気なうちから死後まで、本人の意思に沿った対応が一貫して行える環境が整います。
3.対応がないまま認知症等になった場合との比較
公正証書遺言や任意後見契約などを行わずに、本人が認知症等で判断能力を失った場合、家族は法定後見制度の申立てを行うことを必要とする場合があります。
この制度では、後見人の選任は家庭裁判所が行うため、家族が希望しても親族以外の第三者が後見人に選ばれることがあります。また、本人の意思や希望が明確に確認できない状況下での財産管理や身上保護となるため、関係者間で意見の対立が生じやすくなります。
相続が発生した際にも遺言がない場合は、法定相続分に従って遺産分割協議が必要となり、不仲の相続人や所在不明者がいる場合には、手続きが長期化し、調停等へ発展することもあります。
4.対応していた場合としなかった場合の心情面での比較
本人の立場からの心情
・契約を整えた場合:自ら意思を明確にできたという安心感。誰に何を任せるかを自分で決められたという納得。
・何もしなかった場合:判断能力を失った後、重要な決定が他人の判断に委ねられることへの不安や無力感。
家族の立場からの心情
・契約を整えた場合:本人の意思が明らかであるため、それを尊重して行動できる。迷いや葛藤が少ない。
・何もしなかった場合:後見人の選任や遺産分割をめぐり、家族間で意見が割れやすく、精神的負担が大きい。
5.第三者後見人や裁判所の関与がある場合の特徴
・家族が手続きに関われない場面が増え、制度的な形式は守られる一方で、情緒的な納得感を得にくいことがあります。
6.まとめ
以上を踏まえ、当オフィスではご相談者さまの状況に応じて、公正証書遺言の作成と同時に任意後見契約及び委任契約などを整えておくことの重要性について丁寧に説明しております。
なによりも一番重要なことは、どんなご相談も、ご相談者さま方の意思能力がしっかりとある状態の時でないと何も対策できないということです。
当オフィスへご相談されたときにはすでに何も対策できない状態であることも残念ながら大変多いです。
がんなどの病気の早期発見と同じく、早めのご相談をいただくことで以後のトラブルや無駄な出費、先のストレスなどの軽減につながる対策を講じられる可能性は高まります。
是非ともお知らせの内容をご自身に照らして、予防法務の重要性についてお考えいただく機会となれば幸いです。