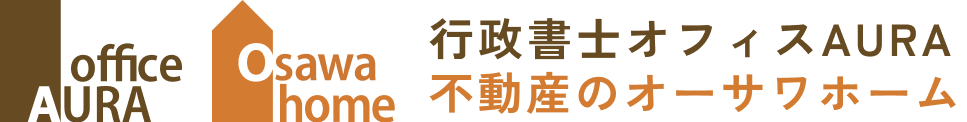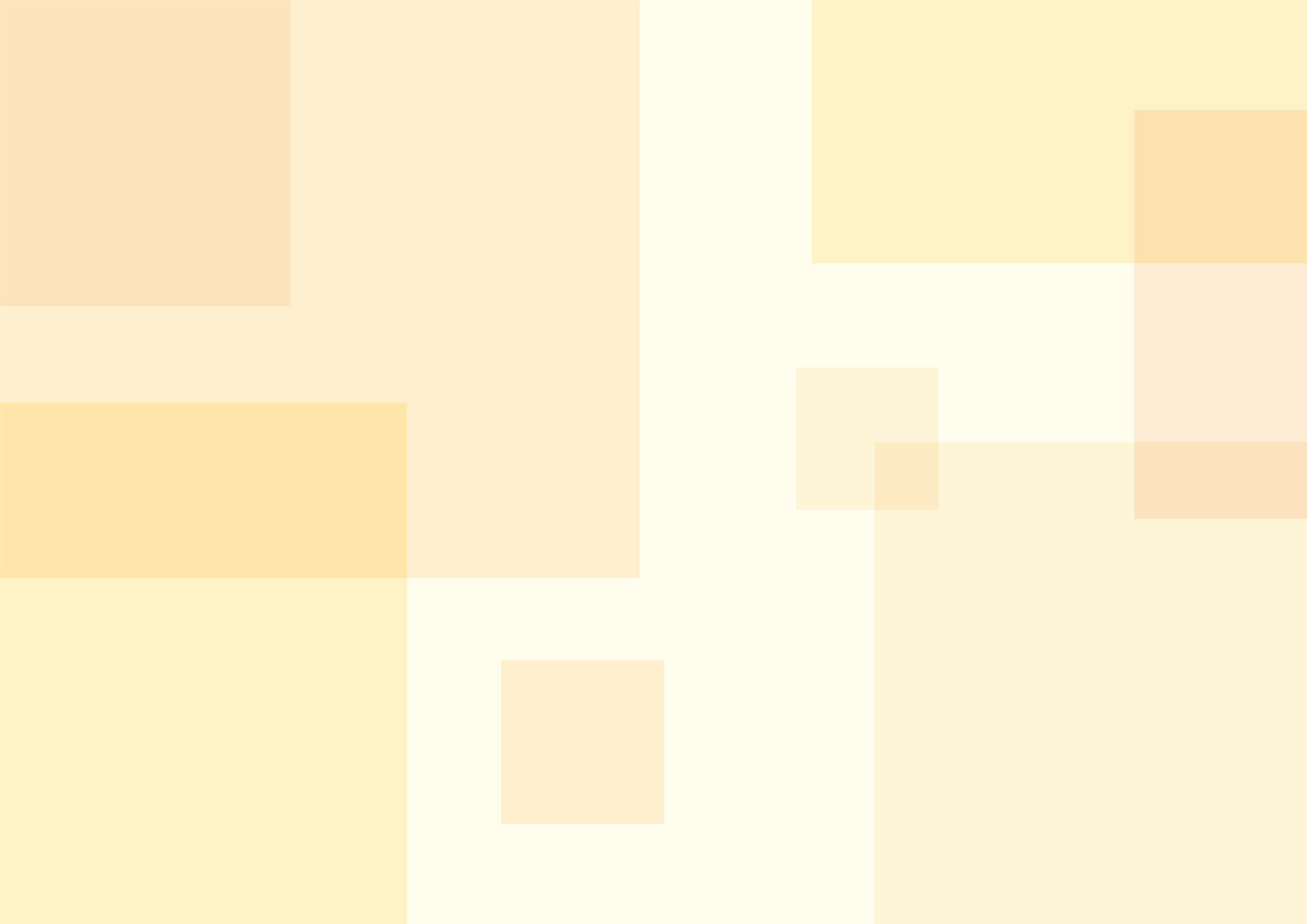いつもご覧いただきありがとうございます。
法定後見制度・任意後見契約・家族信託──それぞれの違いと、メリット・デメリット比較
親の将来が心配になったとき、多くの方が抱えるのが次のような不安です。
「もし認知症になったら、家族はどうすればいいのか」
「財産の管理や手続きは、誰がどうやって進めるのか」
「法定後見制度・任意後見契約・家族信託って、どう違うの?」
制度の名前は聞いたことがあっても、それぞれの内容や使い分けは意外と知られていません。
今回のお知らせでは、代表的な3つの制度――
**「法定後見制度」「任意後見契約」「家族信託」**について、
それぞれの役割と仕組み、メリット・デメリットを一覧比較しながら、
どのようなご家庭に適しているのかを整理していきます。
1.制度ごとの概要と発動条件
| 制度 | 発動のタイミング | 誰が決める? | 必要書類 | 主な使いみち |
|---|---|---|---|---|
| 法定後見制度 | 判断能力が低下してから | 家庭裁判所 | 医師の診断書 等 | 財産管理、契約、施設入所手続き など |
| 任意後見契約 | 元気なうちに契約 → 判断能力低下後に発効 | 本人が決定(公正証書で契約) | 本人・後見人の身分証、公正証書 など | 財産管理、医療手続き、生活支援 など |
| 家族信託 | 判断能力があるうちに信託契約を締結 | 本人と受託者の合意 | 財産目録、信託契約書 等 | 複数不動産の継続管理、資産承継 など |
2.それぞれのメリット・デメリット
法定後見制度(家庭裁判所が関与)
メリット:
- 判断能力がなくなってからでも利用できる
- 家庭裁判所が監督するため、不正を防ぎやすい
デメリット:
- 家族が後見人になれないことも多い(第三者後見人が選任されるケースあり)
- 手続きが煩雑で、費用や時間がかかる
- 柔軟な財産運用ができない(預貯金の引き出し等に制約)
任意後見契約(本人が契約する)
メリット:
- 自分の信頼できる人を後見人に指名できる
- 将来の支援を「契約」で細かく設計できる
- 必要なときにだけ発効する
デメリット:
- 元気なうちに契約しておく必要がある
- 判断能力を失ってからでは契約できない
- 発効には家庭裁判所の手続きが必要(後見監督人選任)
家族信託(契約による信託)
メリット:
- 柔軟な財産管理が可能(不動産賃貸や売却、事業継続など)
- 後見制度に比べて自由度が高い
- 認知症対策だけでなく、相続対策としても活用できる
デメリット:
- 複雑で専門家の関与が必須
- 契約作成費用が高額(数十万円以上かかる場合も)
- 実務に精通した受託者(信頼できる家族等)が必要
- 利用すべきケースは限られる(高額資産・事業管理が前提)
3.一般家庭がまず備えるべきはどれ?
比較した結果からも分かるように、
「法定後見」は最終手段、「家族信託」は特定家庭向けです。
したがって、多くの一般家庭にとってまず優先すべきは、遺言と任意後見契約です。
- 遺言で相続後のトラブルを予防
- 任意後見契約で生前の不安(認知症・介護)に備える
これらを公正証書で明確にしておくことで、
家族間の争いや手続きの混乱を回避できます。
4.「制度を知ること」が第一歩
制度を知らなかったがために、不必要なトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。
- 判断能力を失ってからでは、任意後見契約が締結できない
- 家族信託の内容が複雑すぎて、かえって混乱を招いた
- 法定後見で予想外の第三者が後見人に選ばれてしまった
こうした事態を避けるためにも、「制度の違い」を理解しておくことが大切です。
まずは、ご自身・ご家族にとって必要な制度は何かを把握し、
本当に必要な対策を選択していくことが、将来の安心に直結します。
話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
ご家族だけでは難しい相続の話題も、第三者である専門家が同席することで、落ち着いた話し合いが可能になります。
当オフィスでは、ご家族の立場やお気持ちに配慮しながら、「話し合いの場づくり」を丁寧にサポートしています。
また、公正証書遺言や任意後見契約等の書類作成支援をはじめ、不動産の売買・空き家や古屋の解体・不用品処分・遺品整理・名義変更など、相続に伴う実務を一括で対応。
法律と現場の両面から、ワンストップでご家族の将来を支えます。
「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。
だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。
収拾のつかない紛争となってしまう前に、、、
無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。