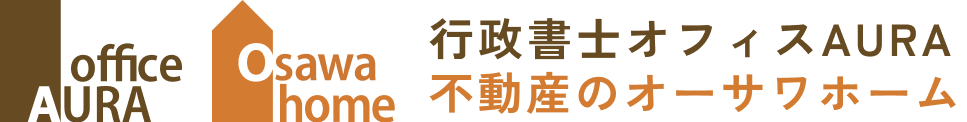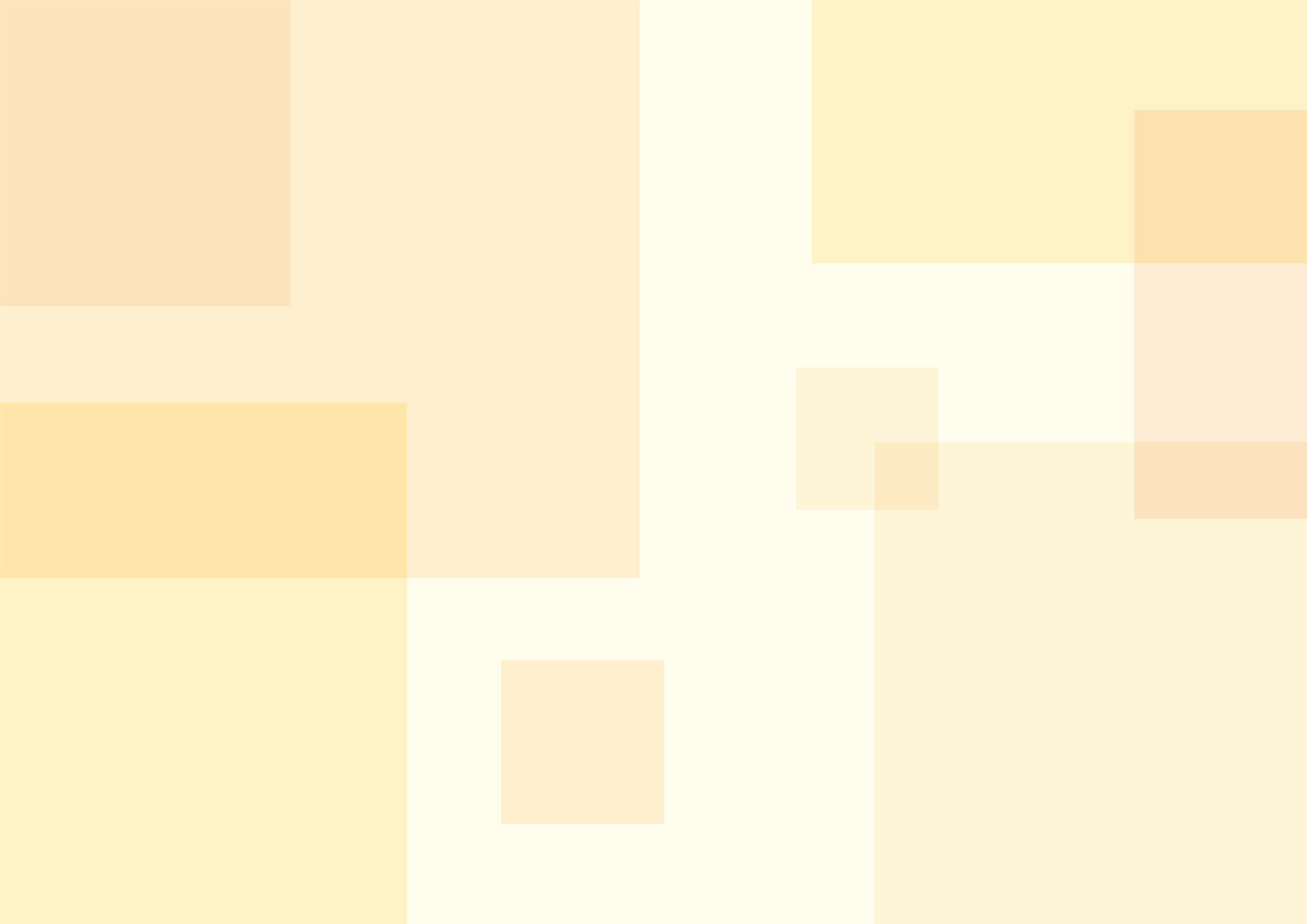いつもご覧いただきありがとうございます。
先日のお知らせでお伝えした通り、今回より5つの具体的な事例を一つずつご紹介いたします。
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
当オフィスでは、ご相談者さま方にしっかりと寄り添い、「話し合いの場づくり」のお手伝いをします。
たとえばこんなケースがあります。
「相続」が「争続」に変わる典型的なケース1~5の概略はこちら。
4.【相続財産の大部分が不動産】分割しにくい財産構成
〈事例〉
Kさん(享年78歳)は、地方都市で50年以上にわたり暮らしてきた自宅を遺して亡くなりました。土地付きの戸建て住宅で、固定資産税評価額は1,800万円。Kさんにとっては長年連れ添った妻との思い出が詰まった、かけがえのない場所でした。
しかし、預貯金は100万円ほどしかなく、実質的な遺産の大部分はこの「自宅不動産」でした。
相続人は、長女Lさん、次男Mさん、三男Nさんの3人。
Lさんは独身で、実家の近くに住んでおり、介護などでもKさんを支えてきました。そのため「父の家に私が住み続けたい」と強く希望します。
一方、MさんとNさんは県外で家庭を持ち、それぞれ住宅ローンを抱える生活。「自宅を売却し、法定相続分どおり3分の1ずつ現金で分けてほしい」と主張しました。
Lさんは「売るくらいなら、私が相続して住む。その代わり、兄たちに代償金(代わりの現金)を払う」と言いましたが、それを納得させるだけの現金がなく、金融機関の借入も審査に通らず断念。
結局、不動産は3人の共有名義となったまま、誰も手を付けることができず、固定資産税だけが毎年課税され、維持管理や掃除、草刈りなどの負担はLさんに集中。「誰がどれだけ手間をかけているか」で不満が積み重なり、兄弟姉妹の関係は次第に冷え込んでいきました。
5年後、Mさんが亡くなり、今度はMさんの妻と子どもが相続人として共有関係に加わることに。その結果、遺産分割どころか「この家をどうするかすら話し合えない状況」へと、問題はより複雑化していきました。
〈教訓〉
このように、遺産の大半が不動産というケースでは、相続人間の調整が非常に難航することが多いのです。特に、以下のような事情がある場合、相続開始後に話し合いで解決するのは至難の業です。
- 相続人の経済状況・生活環境が異なる
- 特定の相続人が同居・介護などで故人と密接だった
- 不動産を現金に変える手段が限られている
こうした争いを未然に防ぐためには、生前の準備が不可欠です。
① 遺言公正証書の作成
不動産の扱いについて、本人の明確な意思があれば、それを遺言で残しておくことが何より重要です。
たとえば「自宅はLに相続させ、代償金として○○万円をM・Nに支払う」といった具体的な内容を記載しておけば、残された子どもたちは「誰が何を引き継ぐのか」で揉めることがなくなります。
また、遺言執行者を第三者に指定しておけば、感情的になりがちな兄弟姉妹間の交渉を避けつつ、法的にスムーズな手続きが可能になります。
② 生命保険などで補填手段を用意
被相続人の預貯金や現金が少くなってからでは、「不動産は特定の子どもに、他の相続人には現金で」という分け方が難しくなります。
そこで有効な方法として、生前、預金や現金が減少してしまわないうちに、生命保険などを活用して、代償金を補填する仕組みを作っておくことです。
例えば、KさんがLさんを受取人とした終身保険を用意し、その保険金を活用してLさんがMさん・Nさんに代償金を支払えるように設計するなど、生命保険を活用して実家を残すことと公平性の両立を図るための補填手段をあらかじめ用意設計することが出来ます。
ただし、生命保険を活用する場合には、契約形態に注意が必要です。
生命保険は便利な補填手段である一方、専門家のアドバイスに基づいて行わなかったことにより、「生命保険契約と相続の法的な関係」をよく理解しないままの契約の保険金が支払われた場合、かえってトラブルの原因になる場合も多く、上記のような契約形態ではなく、一般的な契約形態であったとしても、一度早めに専門家にお願いして現在の契約形態と、相続後に起きうるトラブルの有無の確認、回避策の検討をされることを強くお勧めしています。
なお、「生命保険契約と相続の法的な関係」については、ご相談者さまのみでなく、日頃からお客さまのために尽力し、保険契約をご提唱されている生命保険募集人の方々にも深く理解していただきたいテーマであるため、今後のお知らせにて個別に詳しく取り扱う予定です。
まとめ
「自宅をどう残すか」「誰に引き継がせたいか」――これは多くのご家庭に共通する課題です。
また当オフィスでは、相続後共有になった不動産に、近くに住む兄弟姉妹が住み続けているので手が出せずに困っているとの県外相続人の方からの相談も多くあります。
特に、不動産が主な資産であるご家庭では、何も準備がなければ**相続人全員の意見が一致するまで動かせない“共有地獄”**に陥る危険性があります。
大切な住まいを、家族の絆を壊す“火種”にしないためにも、遺言と併せて資金の補填手段(保険や生前贈与)の活用についてなど、真剣に考える機会にしていただけると幸いです。。
話しにくい話題こそ、「第三者」が入る意味があります
相続の準備といえば「遺言書」と思い浮かべる方は多いものの、それ以前の段階——つまり、家族で相続の話題をきちんと話し合える環境を整えることが、実は最も重要で、かつ難しい部分です。
当オフィスでは、ご相談者さま方にしっかりと寄り添い、「話し合いの場づくり」のお手伝いをします。
- 家族だけでは切り出しにくい「相続の話題」に、専門家として第三者の立場から同席
- 相続人となる方々の立場や気持ちを整理しながら、話し合いを前向きに進めるための助言
- 判断能力があるうちに、公正証書遺言・任意後見契約・委任契約などの準備をスムーズに実施
相続や遺言のご相談は、「民亊法務の専門家」と「実務の現場」を知る当オフィスにお任せください。
当オフィスでは、行政からの許認可を受けたうえで、遺言・相続・任意後見契約などの民事法務を中心に、書類作成から公正証書の手配まで一貫して対応しております。
さらに、不動産の売買、建物の解体、不用品処分、遺品整理、不動産の相続手続き、名義変更に関する書類作成のご支援までワンストップでの対応が可能です。
法律だけでなく、現実に必要となる作業までを一括でご相談いただけるため、ご家族の負担を最小限に抑え、安心して将来に備えることができます。
「まだ早いかも」と思った今こそ、最適なタイミングです
相続準備は、「何か起きてから」では間に合わないことが多くあります。
「家族のもめごとを避けたい」「今は元気だけど、いずれに備えたい」
そう感じたときが、準備を始めるベストタイミングです。
「まだ早いかな」「家族にどう切り出せばいいかわからない」「どこに相談したらいいのかわからなかった」という声を私たちはたくさん聞いてきました。
だからこそ、その一歩を一緒に踏み出すための伴走者として、私たちがお役に立てればと思っています。
無料相談から承っております。当オフィスまで、どうぞお気軽にご連絡ください。スまで、どうぞお気軽にご連絡ください。