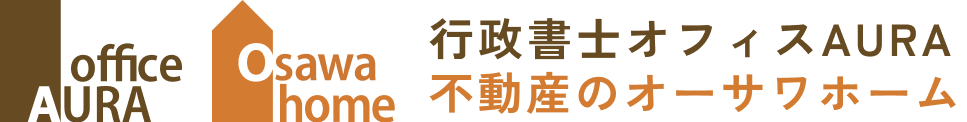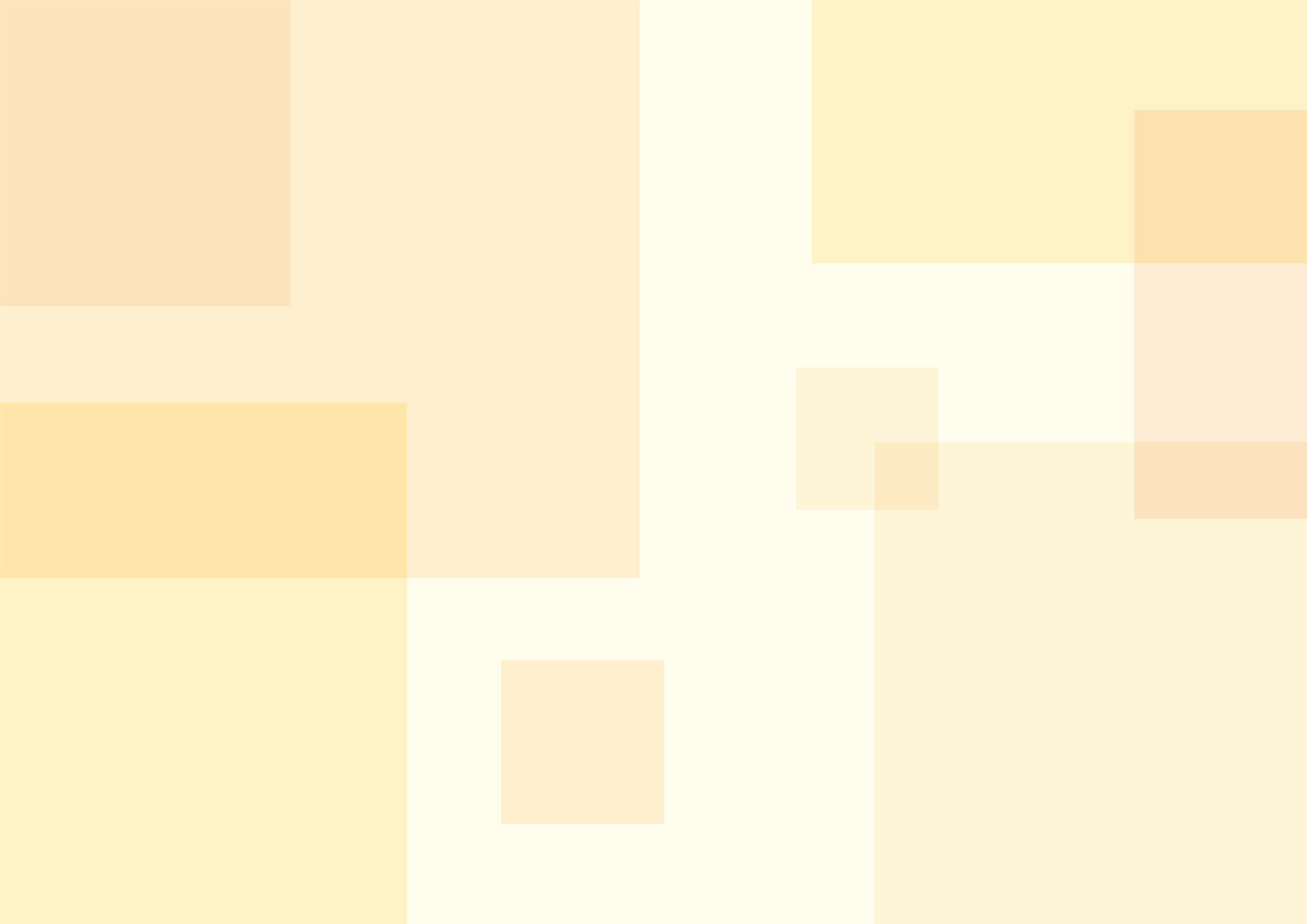いつもご覧いただきありがとうございます。
当オフィスでは、役所手続きにつき、建設業許可や産廃収集運搬業許可、宅建業免許申請以外にも、近日ご依頼のあった古物営業法に基づく古物商許可申請のサポートも行っております。
近年、リユースビジネスやフリマアプリの普及に伴い、古物商許可が必要なケースが増加しています。
この度のお知らせでは、
- 古物商許可が必要な業種や最近の申請傾向
- 無許可営業による罰則とリスク
- 許可が不要なケースとの違い
- 法改正による手続きの変化
などを詳しく解説しながら、専門家に依頼するメリットについてもご紹介いたします。
目次
1.古物商許可が必要な業種とは?
「古物」とは一度でも使用された物品、または使用されていない物でも取引されたことがある物を指します。
これを仕入れて売買する業を「古物営業」と言い、以下のような事業者には古物商許可が必要です。
主に対象となる業種(例)
- リサイクルショップの運営
- 中古自動車・中古バイクの販売
- 中古ブランド品・時計・宝石の売買
- 金券ショップ
- フリマアプリやネットオークションを利用して継続的に中古品を転売している個人・法人
最近許可申請が増加している業種
近年では次のような分野で古物商許可の申請が急増しています:
- フリマアプリやメルカリ・ヤフオク転売(副業)
- 中古家電の再販売業者
- YouTuber・インフルエンサーによる私物の販売ビジネス
- 中古アウトドア用品の再販業
- 遺品整理業者、不用品回収業者(リユース目的がある場合)
2.古物商許可を得ずに営業した場合のペナルティ
無許可で古物営業を行った場合、古物営業法第31条に基づき処罰の対象となります。
主なペナルティ
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 情状により**併科(両方同時に課される)**されることもあります
- 警察による立入検査、行政処分
- 一度摘発されるとその後の許可取得が困難に
「知らなかった」では済まされないのが古物営業の実務です。早めの対応が重要です。
3.直近の法改正とその影響
古物営業法は2020年(令和2年)4月1日に大きな改正が施行されました。
その中でも事業者にとって特に影響が大きいのが**「営業所等の届け出制度の緩和」**です。
① 許可が「不要な場合」と「必要な場合」の取引の違い
| 取引の内容 | 許可の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 自分の不要品を売る(1回きり) | 不要 | 不用品の処分目的であれば許可は不要 |
| 不要品を何度も販売し、収益を得ている | 必要 | 繰り返し性・営利性があると判断される |
| 他人から買い取って販売する | 必要 | 明確な古物営業に該当 |
| 仕入れた中古品をネットで販売 | 必要 | オンラインかどうかは関係なし |
| ハンドメイドや新品商品の販売のみ | 不要 | 一度も流通していない物は対象外 |
| 家族や知人にだけ譲渡 | 不要 | 営業性がないため |
※個人事業主、副業でも繰り返し収益目的なら許可が必要になります。
②法改正前後の手続きの違い
| 項目 | 改正前 | 改正後(2020年4月~) |
|---|---|---|
| 営業所ごとに許可が必要 | はい | いいえ(一括許可) |
| 営業所の追加・削除の手続き | 新たに許可取得 | 届け出だけでOK |
| 出張買取など移動営業 | 許可地域ごとに申請 | 全国一括許可が基本に |
| 標識掲示のルール | 地域・業種による違いあり | 全国で統一の記載様式へ |
メリット
- 営業エリアの拡大がしやすい
- 許可申請の回数や費用が削減
デメリット
- 管理責任が一元化され、帳簿記録や報告義務が厳格化
4.なぜ専門家に相談すべきなのか?
古物商許可申請には、以下のような「見えづらいハードル」があります:
- 誤った申請区分で再申請になる
- 役員の過去の経歴(欠格事由)で却下されることがある
- 書類の不備で審査が長期化
- 営業所・倉庫の使用権限の証明が難しい場合も
当オフィスでは、申請書類の作成はもちろん、事前の警察署との調整や、不要な再申請を避けるための事前診断までトータルで対応しております。
副業で中古品販売を考えている方、既に営業を始めている方、不用品回収・遺品整理の業務を始めたい方など、状況に応じたアドバイスが可能です。
いつでもお気軽に当オフィスまでご相談ください。